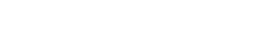博多献上

「献上」の名称由来

慶長5年(1600年)黒田長政が筑前を領有するようになってからは、幕府への献上品として博多織を選び、毎年3月に帯地十筋と生絹三疋を献上するようになりました。
その模様は仏具の「独鈷」と「華皿」との結合紋様と中間に縞を配した定格に固定されていました。
それ以前は単に独鈷、華皿浮け柄といわれていたものが、それ以来「献上」と呼称されるようになったのです。
(写真:上「華皿」、下「独鈷」)

- 独鈷(どっこ)
- 密教法具の一つ。真言宗では、煩悩を破砕し、菩薩心を表わす金属製の仏具であり、修法に用いられます。細長く手に握れるほどの大きさで、中程がくびれ両端がとがっています。
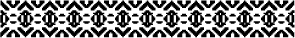
↑独鈷を図案化した模様 - 華皿(はなざら)
- 元来は仏具の一種。仏の供養をするとき、花を散布するのに用いられる器です。
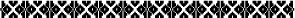
↑華皿を図案化した模様 - 縞(しま)
- 献上の模様の「縞」には両子持(りょうこもち)と中子持(なかこもち)を使います。

↑両子持(孝行縞)

↑中子持(親子縞)